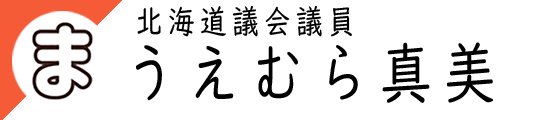令和3年第1回定例会での ■空知特集④■
一般質問にて「中小企業の支援について」
・北海道の中小企業は、大手企業の関連工場等も多く、コロナ禍による経営不振で、大手企業側からの製造縮減や工場廃止を余儀なくされるケースが懸念される。
・現に、私の地元では、芦別市内スーツ製造工場が閉鎖し、ふるさと納税が9割減、また、夕張市内では冷凍食品工場などが閉鎖と縮小を強いられ、さらに夕張リゾート運営会社が破綻となり、市内コンビニエンスストアや飲食店では夕張リゾートがなくなってしまうと今後の経営継続が不安だという声も多く、地域全体の経済の低迷が心配されている。
・芦別市では約100名、夕張市では約200名の方々が新たな働き場を求めているのに対し、地域の事情としては、夏の働き場はあったとしても、一年通して雇用するところが難しいなど地元経営者の話を伺っているところです。
・働き場を求めて戸惑う方々のサポートを道でも行っていただいているところですが、その地域で雇用の受け皿がない場合、ますます人口減少が加速し、地域の衰退に直面する恐れがある、そういったことが現実味を帯びている。
・新型コロナウィルス感染症の影響は今後も続くことが予測される中で、そのような事態を軽減するためにも、今の段階から、中小企業の技術力を無駄にすることなく、企業間の連携やマッチングを通して新事業の可能性を見出すサポートが必要になっていると思いますが。
(答弁)
・本道の中小企業は、感染症の長期化の影響、大規模製造業の事業再編などから、厳しい経営環境。
企業の技術力向上、企業間連携などによる新事業への進出が重要。
・道では、企業の技術力の向上に向け、専門家派遣や産業支援機関などを通じた技術指導、企業間連携による製品開発や取引拡大に向け、共同研究開発への補助や受注商談会などに取り組んでいる。
・金融機関とも連携を図り、「後継者人材バンク」を通じて、優れた技術力を有する企業の円滑な事業継承を進めている。
今後も、道の相談窓口、市町村・商工団体への施策説明会などにより、支援施策の積極的な活用促進に努め、経営環境の変化に対応した企業の新たな事業展開を支援。
___________↓☆↓☆↓☆↓
緊急雇用対策プログラムも設置し、雇用の安定に対して道と各市町村も連携をしているが、地域の実情を見ると追いついていないと感じている。
コロナ禍で、都会から地方を求めて移住をする方もいる一方で、自然減と合わせて社会人口減の加速がとても心配されるところであります。
地方の経済を支える中小企業の対策は、その会社がなくなってから、閉鎖してからでは遅いです。その前から、各市町村単位でも支援の対応対策を強化するなど考えなければ、多くの住民が働く工場が急になくなってしまうと地域の経済に与える打撃も大きいと思います。
★事前の対策として、この度道としても支援事業[中小企業競争力強化促進事業]
の募集が始まりました。(コロナでダメージを受けている企業やコロナだけではなく事前にいろいろと考えている企業などすべての中小企業が対象になります)
↓↓↓
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/kyosoryoku2.pdf
★もし、詳細を知りたい場合は、各中小企業支援センターに問い合わせください。
中小企業競争力強化促進事業問合せ先
↓↓↓
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/kyosoryoku1.pdf
※この事業は、製品開発や販路拡大に向けて取組事業に対し、補助金として1/2支援されるものです。4月21日~5月31日まで募集期間、審査会を経て採択されるかが決まります。すべての応募が通るわけではありません。